今月は今までの月間最高乳がん手術症例数を更新しそうな勢いです。4-5月は少し症例数が減りましたが、6月を過ぎてから徐々に増えて7月は関連病院からの紹介も含めて続々と乳がんが見つかっています。
ただ、残念なことにここのところの症例は進行がんが多いようです。先週は術前化学療法を拒否した局所進行乳がん(1例は炎症性乳がん)の手術が2件ありました。術後の化学療法も今のところ同意が得られていないため、可能な限りの外科的切除を行ないました。久しぶりに一昔前のような拡大手術になってしまいました。
ぎりぎりまで我慢した上、化学療法を拒否されてしまうと、私たちは何もできない無力感に苛まされます。せめてもっと早く受診していたら手術だけで治ったかもしれない、術前化学療法を行なえばもっと侵襲の少ない手術で済んだのに…と思いますが、患者さんにはそれぞれそこに至った事情があるようですのでやむを得ません。でもとても残念に思います。病理結果が出たら再度化学療法に同意してもらえないか説得するつもりです。
私たちの病院では相変わらず高齢者や合併症を持った患者さんは多いですが、最近は若い患者さんも増えてきています。来週は20才台の患者さんの手術があります。30才台前半の患者さんもぽつぽついらっしゃいます。これからはもっと多くの若い患者さんたちに選んでもらえるような乳腺センターにしていきたいと思っています。今年は過去最高の手術件数になりそうですが、3人体制になったことですし、まだ余力はあります。近々近隣の検診施設に患者さんを紹介していただけるようにご挨拶に伺う予定です。
乳癌が心配だけど、どこに受診したらいいかわからない、乳癌になってしまって不安…、再発したからもうだめかもしれない…。そんな不安や悩みに少しでもお役に立てればと思って始めてみました。 (*投稿内容と無関係なコメント、病状のご相談はご遠慮願います*)
2011年7月16日土曜日
2011年7月13日水曜日
乳腺症 vs 非浸潤がん〜微妙な病変
最近、診断に苦慮する微妙な病変が連続しています。
乳腺症の一部のように見えますが前にはなかった所見ですとか、乳腺症のムラが局所的に目立つなどの所見が指摘されて、細胞診で「鑑別困難」(乳腺症 vs 非浸潤がん)という判定となることは今までもありました。
こういう場合、かなり前は悪性の疑いが一定以上あれば「Probe lumpectomy(試験的乳腺部分切除術)」を行なって診断的治療を行なっていましたが、最近ではまず針生検(コアニードル・バイオプシー:CNB)を行なって、だいたいは良悪の診断がついていたのです。ところが、ここのところの症例は、針生検を行なっても「鑑別困難(乳腺症 vs 非浸潤がん)」というケースが連続していて頭を悩ませています。ほとんどの病変が良性(乳腺症)なのですが、ごく一部の乳管内に非浸潤がんを思わせる病変が混在しているため、このような診断になっているのです(量的に十分な病変がなければ「非浸潤がん」と診断するのは困難な場合があります)。
超音波技師さんたちが必死に病変を探してくれるため、このような微妙なものが見つかってくるのだと思います。大変ありがたいことではありますが、悩ましくもあります。できるだけ太めの針で何本も検体を採取するのですが、本来はマンモトームで生検するほうが情報量が多いので、そろそろ針生検(CNB)に頼るのは限界なのかもしれません。
マンモトーム導入に消極的なG先生、そろそろ購入を検討してみませんか?
乳腺症の一部のように見えますが前にはなかった所見ですとか、乳腺症のムラが局所的に目立つなどの所見が指摘されて、細胞診で「鑑別困難」(乳腺症 vs 非浸潤がん)という判定となることは今までもありました。
こういう場合、かなり前は悪性の疑いが一定以上あれば「Probe lumpectomy(試験的乳腺部分切除術)」を行なって診断的治療を行なっていましたが、最近ではまず針生検(コアニードル・バイオプシー:CNB)を行なって、だいたいは良悪の診断がついていたのです。ところが、ここのところの症例は、針生検を行なっても「鑑別困難(乳腺症 vs 非浸潤がん)」というケースが連続していて頭を悩ませています。ほとんどの病変が良性(乳腺症)なのですが、ごく一部の乳管内に非浸潤がんを思わせる病変が混在しているため、このような診断になっているのです(量的に十分な病変がなければ「非浸潤がん」と診断するのは困難な場合があります)。
超音波技師さんたちが必死に病変を探してくれるため、このような微妙なものが見つかってくるのだと思います。大変ありがたいことではありますが、悩ましくもあります。できるだけ太めの針で何本も検体を採取するのですが、本来はマンモトームで生検するほうが情報量が多いので、そろそろ針生検(CNB)に頼るのは限界なのかもしれません。
マンモトーム導入に消極的なG先生、そろそろ購入を検討してみませんか?
2011年7月10日日曜日
乳がん再発治療研究会2
乳がんの初期治療に関しては、手術、放射線治療、術後補助療法、そして術前療法とさまざまな研究が世界中で行なわれてきて、この20年の間に飛躍的な進歩を遂げました。
一方、再発に対する治療は未だに十分なガイドラインができているとは言えない状況です。そして、患者さんを含めた一般の人たちはもちろん、私たち自身も再発治療に関して様々な疑問を持っています。
例えば、
①再発したら治癒は不可能なのか?
②再発巣が消えて何年経過したら治癒と判断できるのか?
③治癒できる可能性があるとしたら、それはどのようなタイプでどのような再発形式なのか?
④再発に対する外科治療は、本当に外科医の自己満足だけで無意味なことなのか?
⑤延命効果は何ヶ月以上あれば有意義だと言えるのか?
などです。
これらの命題を解決するための検討は、一つの施設の症例だけでは困難な場合が多いのです。同じような経験を集積して検討しなければなりません。そのために多施設で検討できる場が欲しいと思っていました。
研究会の内容としては、例えば、各施設で再発治療後に治癒した症例を初再発部位別に集め、そのサブタイプなどのがんの性質や治療内容を検討する、同じような状況の再発患者さんに対して全身療法に局所治療を加えた群と加えなかった群の生存率、平均生存期間を比較する、この20年間の治療法の進歩で再発治療においても生存期間や生存率に進歩がみられたのか、などを考えています。
どのようなメンバーでどのように研究会を立ち上げていけばいいのか、少し時間をかけて考えてみたいと思います。
一方、再発に対する治療は未だに十分なガイドラインができているとは言えない状況です。そして、患者さんを含めた一般の人たちはもちろん、私たち自身も再発治療に関して様々な疑問を持っています。
例えば、
①再発したら治癒は不可能なのか?
②再発巣が消えて何年経過したら治癒と判断できるのか?
③治癒できる可能性があるとしたら、それはどのようなタイプでどのような再発形式なのか?
④再発に対する外科治療は、本当に外科医の自己満足だけで無意味なことなのか?
⑤延命効果は何ヶ月以上あれば有意義だと言えるのか?
などです。
これらの命題を解決するための検討は、一つの施設の症例だけでは困難な場合が多いのです。同じような経験を集積して検討しなければなりません。そのために多施設で検討できる場が欲しいと思っていました。
研究会の内容としては、例えば、各施設で再発治療後に治癒した症例を初再発部位別に集め、そのサブタイプなどのがんの性質や治療内容を検討する、同じような状況の再発患者さんに対して全身療法に局所治療を加えた群と加えなかった群の生存率、平均生存期間を比較する、この20年間の治療法の進歩で再発治療においても生存期間や生存率に進歩がみられたのか、などを考えています。
どのようなメンバーでどのように研究会を立ち上げていけばいいのか、少し時間をかけて考えてみたいと思います。
2011年7月8日金曜日
乳がん再発治療研究会1
私のライフワークの一つが乳がんの再発治療です。
一般的には乳がんがひとたび再発すると、治癒は困難と言われています。もちろん、実際多くの場合、完全に治癒させるのは難しいのはその通りです。しかし、中には再発治療後、まったく再発なく長期に経過している患者さんもいらっしゃるのです。私の経験上でも再発が治癒したと思われる患者さんは何人もいらっしゃいます。
そもそも遠隔転移したら治癒しないという考え方は正しくないと私は信じています。その根拠は、術後補助療法によって生存率が改善するという事実があるからです。このことは、手術時に存在していた微小転移(何もしなければ将来顕在化して生命を脅かした)を補助療法によって根絶できた患者さんが一定数いるということを意味しています。そうでなければ術後補助療法で生存率は改善しないはずだからです。
術後補助療法で微小転移を根絶できるのであれば、再発でもある条件を満たせば完治できる可能性があるのではないか?というのが、私が再発治療をライフワークに選んだ原点です。
新病院建設に向けて、私たちの病院も少しずつ変わりつつあります。その一つが積極的な学術研究活動へのバックアップです。今までは製薬会社との共催の研究会などに関しては消極的でしたが、最近では後押ししてくれるようになってきています。先日も院長から、乳腺センターで研究会を立ち上げてはどうだ?と言われました。
乳腺関連の小規模の研究会はたくさんあります。そのほとんどは、症例検討会などの診断に関するものや最新の医療機器や新薬の講演、ASCOなどの学会レポートなどが中心です。本当の意味での自分たちが中心になった研究会というのは少なく、特に再発治療に特化した研究会は少ないということに気づいたので、もし立ち上げるなら再発治療、特に長期延命や治癒を目指した研究会にしようと決めました。
製薬会社数社に声をかけてみましたが、好意的に考えてくれていますので実現できそうな雰囲気です。これから年内発足に向けて準備をしていこうと考えています。
一般的には乳がんがひとたび再発すると、治癒は困難と言われています。もちろん、実際多くの場合、完全に治癒させるのは難しいのはその通りです。しかし、中には再発治療後、まったく再発なく長期に経過している患者さんもいらっしゃるのです。私の経験上でも再発が治癒したと思われる患者さんは何人もいらっしゃいます。
そもそも遠隔転移したら治癒しないという考え方は正しくないと私は信じています。その根拠は、術後補助療法によって生存率が改善するという事実があるからです。このことは、手術時に存在していた微小転移(何もしなければ将来顕在化して生命を脅かした)を補助療法によって根絶できた患者さんが一定数いるということを意味しています。そうでなければ術後補助療法で生存率は改善しないはずだからです。
術後補助療法で微小転移を根絶できるのであれば、再発でもある条件を満たせば完治できる可能性があるのではないか?というのが、私が再発治療をライフワークに選んだ原点です。
新病院建設に向けて、私たちの病院も少しずつ変わりつつあります。その一つが積極的な学術研究活動へのバックアップです。今までは製薬会社との共催の研究会などに関しては消極的でしたが、最近では後押ししてくれるようになってきています。先日も院長から、乳腺センターで研究会を立ち上げてはどうだ?と言われました。
乳腺関連の小規模の研究会はたくさんあります。そのほとんどは、症例検討会などの診断に関するものや最新の医療機器や新薬の講演、ASCOなどの学会レポートなどが中心です。本当の意味での自分たちが中心になった研究会というのは少なく、特に再発治療に特化した研究会は少ないということに気づいたので、もし立ち上げるなら再発治療、特に長期延命や治癒を目指した研究会にしようと決めました。
製薬会社数社に声をかけてみましたが、好意的に考えてくれていますので実現できそうな雰囲気です。これから年内発足に向けて準備をしていこうと考えています。
2011年7月4日月曜日
エリブリン(商品名 ハラヴェン)続報
乳癌の治療最新情報22(http://hidechin-breastlifecare.blogspot.com/2010/11/22.html)でもお報せしましたが、いよいよエリブリン(商品名 ハラヴェン)が日本でも4月に認可され、7月中に発売になりそうです。
適応は、「アントラサイクリン系およびタキサン系抗がん剤での治療歴を含む化学療法施行後の手術不能または再発乳がん」とのことです。エリブリンは海外第Ⅲ相試験(EMBRACE試験)において、単剤で初めて、前治療歴のある進行または再発乳がんにおける全生存期間(OS)を有意に延長した薬剤です(エリブリン投与群 vs 主治医選択治療群の全生存率 13.2ヵ月 vs 10.5ヵ月、ハザード比:0.81、p=0.014)。
ただ、安全性については骨髄抑制が高頻度に認められており、とくに好中球減少が多く認められているため、注意が必要です。
この薬剤の特長として、投与時間の短さ(2-5分の静注または点滴)と簡便さ(過敏反応予防のステロイドなどの前処置が不要)が挙げられます。したがって投与ルート確保、投与、フラッシングまでを約30分で終えることができ、患者さんと看護師の負担を軽減できます。外来化学療法室での投与に非常に適した治療と言えると思います。
アンスラサイクリン、タキサン耐性乳がんの治療手段に新たな薬剤が加わることは、再発治療中の患者さんにとって、光明だと思います。私の患者さんの中にも待っている患者さんがいらっしゃいます。ただ、新薬ですので十分に注意して投与しなければなりませんね。
適応は、「アントラサイクリン系およびタキサン系抗がん剤での治療歴を含む化学療法施行後の手術不能または再発乳がん」とのことです。エリブリンは海外第Ⅲ相試験(EMBRACE試験)において、単剤で初めて、前治療歴のある進行または再発乳がんにおける全生存期間(OS)を有意に延長した薬剤です(エリブリン投与群 vs 主治医選択治療群の全生存率 13.2ヵ月 vs 10.5ヵ月、ハザード比:0.81、p=0.014)。
ただ、安全性については骨髄抑制が高頻度に認められており、とくに好中球減少が多く認められているため、注意が必要です。
この薬剤の特長として、投与時間の短さ(2-5分の静注または点滴)と簡便さ(過敏反応予防のステロイドなどの前処置が不要)が挙げられます。したがって投与ルート確保、投与、フラッシングまでを約30分で終えることができ、患者さんと看護師の負担を軽減できます。外来化学療法室での投与に非常に適した治療と言えると思います。
アンスラサイクリン、タキサン耐性乳がんの治療手段に新たな薬剤が加わることは、再発治療中の患者さんにとって、光明だと思います。私の患者さんの中にも待っている患者さんがいらっしゃいます。ただ、新薬ですので十分に注意して投与しなければなりませんね。
2011年7月3日日曜日
「健康まつり」と乳がん触診モデル
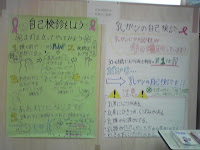


今日、毎年恒例の病院主催のイベント、「健康まつり」が行なわれました。ポスターなどを掲示して病気の予防などの啓蒙をしたり、職員や地域の方々が飲食物やスーパーボールすくいなどの出店や歌・踊りなどのステージ発表を行なったりして、多くの方々が集まるイベントです。
恒例とは言いつつ、まともに参加したのは久しぶりでした。今回は外科外来で乳がん検診の啓蒙活動をするということでしたので、看護師さんに自己検診法を指導してポスターを作成し、掲示しました(写真1枚目)。また、乳腺センターの備品申請で乳がんの触診モデル(写真2、3枚目)を2種類購入したので、それも活用してもらうことにしました。この触診モデルは、京都科学というメーカーで作成しているものです。箱に固定されたタイプと首からもかけれるタイプがあり、それぞれに、がんや良性腫瘍に似せたしこりを埋め込んであります。えくぼ症状を呈するしこりもあり、なかなか巧妙に作られています。ただ、若干乳房が硬いので触診に力が必要です。せっかく購入した触診モデルですので、今後いろいろな場所に積極的に出かけて乳がん検診の啓蒙活動に役立てようと思っています。
今日は少し風が強かったのですが、とても良い天気でなによりでした。入院患者さんも車椅子などで来て下さっていましたが、楽しそうに笑顔を見せてくれていました。ただ、屋内の啓蒙ポスターのエリアへの人の流れが少なかったように見えましたので、来年はこちらにも多くの人が注目してくれるような工夫が必要ではないかと感じました。来年はもう少し積極的に関わってみようかなと思いました。
2011年7月1日金曜日
アロマターゼ阻害剤の乳がん発生予防効果
タモキシフェンによる乳がん発生の予防効果についての報告はかなり以前からあります。またタモキシフェンの仲間のラロキシフェンにも同様の作用があることが報告されています(http://www.medpagetoday.com/MeetingCoverage/AACR/19653)。しかし、閉経後の乳がん術後再発予防効果においてタモキシフェンより効果が高いと考えられているアロマターゼ阻害剤の乳がん発生予防効果については今まで充分にされていませんでした。
今回ようやくThe New England Journal of Medicine 2011; 364: 2381-2391にエキセメスタンによる閉経後女性の乳がん予防効果が報告されました。概要は以下の通りです。
報告者:Paul E. Gossら(米マサチューセッツ総合病院がんセンター)
対象:2004年2月〜10年3月に登録された35才以上の閉経後女性のうち以下の条件を満たした4,560例。
(1)60歳以上,(2)乳がん発症リスクを推計するGailの5年リスクスコアが1.66%超,(3)異型乳管過形成,異型小葉過形成,上皮内小葉がん,乳腺切除を伴う非浸潤性乳管がんのいずれかの既往—に1つ以上当てはまること。
方法:対象者を,エキセメスタン群2,285例(年齢中央値62.5歳)とプラセボ群2,275例(同62.4歳)にランダムに分類し、各患者群に,エキセメスタン25mg/日もしくはプラセボを最長5年間もしくは乳がん発症まで投与した。一次評価は浸潤性乳がん発症率とした。
結果:追跡期間の中央値35カ月におけるプラセボ群と比較した浸潤性乳がんの年間発症率は65%低下(0.19% vs 0.77% HR 0.35 p=0.002)、浸潤性+非浸潤性乳がんでは53%減少した(0.35% vs 0.77% HR 0.47 p=0.004)。
また,年間発症率は非浸潤性乳管がんでは0.16% vs 0.24%,異型乳管過形成,異型小葉過形成,上皮内小葉がんの3種を合わせた場合では0.07% vs 0.20%と,いずれもエキセメスタン群はプラセボ群に比べて低かった。
顔面紅潮,疲労感,不眠,下痢,関節炎などの副反応発生数はエキセメスタン群で高頻度だったが、心血管系イベント(106% vs 111%,P=0.78),臨床的な骨折(149% vs 143%,P=0.72),新規の骨粗鬆症(37% vs 30%,P=0.39),その他のがん(43% vs 38%,P=0.58)などの重篤な副反応に有意差は認めなかった。
結論:プラセボの投与に比べ,エキセメスタンの投与により,浸潤性乳がんの年間発症リスクは65%低下することが認められた。さらにエキセメスタンは,浸潤性乳がんの前駆病変である非浸潤性乳管がん,異型乳管過形成,異型小葉過形成,上皮内小葉がんの発症リスクも減少されることが分かった。
まだ観察期間が短いこと、対象者をどう選択するか、投与期間はどのくらいが適切か、などの課題はありますが、少なくともハイリスク症例に対する乳がん発生予防の選択手段の一つとして期待できそうです。
今回ようやくThe New England Journal of Medicine 2011; 364: 2381-2391にエキセメスタンによる閉経後女性の乳がん予防効果が報告されました。概要は以下の通りです。
報告者:Paul E. Gossら(米マサチューセッツ総合病院がんセンター)
対象:2004年2月〜10年3月に登録された35才以上の閉経後女性のうち以下の条件を満たした4,560例。
(1)60歳以上,(2)乳がん発症リスクを推計するGailの5年リスクスコアが1.66%超,(3)異型乳管過形成,異型小葉過形成,上皮内小葉がん,乳腺切除を伴う非浸潤性乳管がんのいずれかの既往—に1つ以上当てはまること。
方法:対象者を,エキセメスタン群2,285例(年齢中央値62.5歳)とプラセボ群2,275例(同62.4歳)にランダムに分類し、各患者群に,エキセメスタン25mg/日もしくはプラセボを最長5年間もしくは乳がん発症まで投与した。一次評価は浸潤性乳がん発症率とした。
結果:追跡期間の中央値35カ月におけるプラセボ群と比較した浸潤性乳がんの年間発症率は65%低下(0.19% vs 0.77% HR 0.35 p=0.002)、浸潤性+非浸潤性乳がんでは53%減少した(0.35% vs 0.77% HR 0.47 p=0.004)。
また,年間発症率は非浸潤性乳管がんでは0.16% vs 0.24%,異型乳管過形成,異型小葉過形成,上皮内小葉がんの3種を合わせた場合では0.07% vs 0.20%と,いずれもエキセメスタン群はプラセボ群に比べて低かった。
顔面紅潮,疲労感,不眠,下痢,関節炎などの副反応発生数はエキセメスタン群で高頻度だったが、心血管系イベント(106% vs 111%,P=0.78),臨床的な骨折(149% vs 143%,P=0.72),新規の骨粗鬆症(37% vs 30%,P=0.39),その他のがん(43% vs 38%,P=0.58)などの重篤な副反応に有意差は認めなかった。
結論:プラセボの投与に比べ,エキセメスタンの投与により,浸潤性乳がんの年間発症リスクは65%低下することが認められた。さらにエキセメスタンは,浸潤性乳がんの前駆病変である非浸潤性乳管がん,異型乳管過形成,異型小葉過形成,上皮内小葉がんの発症リスクも減少されることが分かった。
まだ観察期間が短いこと、対象者をどう選択するか、投与期間はどのくらいが適切か、などの課題はありますが、少なくともハイリスク症例に対する乳がん発生予防の選択手段の一つとして期待できそうです。
登録:
投稿 (Atom)