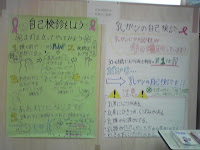石灰化というのは、何らかの原因でカルシウムが沈着したものを言います。石灰化には良性の石灰化と悪性の石灰化があり、良性の石灰化が悪性に変わるということはありません。ただ、初期の悪性石灰化は良性の石灰化と区別がつかないことはあります。ですから、前回のマンモグラフィとの比較が非常に有用な場合があります。
一目見て良性と判断できる石灰化には、動脈硬化、嚢胞の石灰化、古い線維腺腫の石灰化などがあります(カテゴリー1または2)。
問題は良性か悪性化の鑑別が必要な石灰化です。これをカテゴリー2(良性)から5(悪性)までにカテゴリー分類するのですが、これは2つの要素を組み合わせて判断します。
1つ目は、石灰化一つ一つの形状です。微小円形→淡く不明瞭→多形性(ガラスを割ったかけらのような形)→微細線状・微細分枝状(木の枝のような形状)の順で悪性の比率が高くなります。
2つ目は石灰化の分布です。びまん性・領域性(乳管の走行=腺葉に一致しないぱらぱらとした分布)→集簇性(狭い範囲に集まっている)→線状・区域性(乳管の走行=腺葉に一致した分布)の順で悪性の可能性が高くなります。
例えば、微小円形の石灰化が、びまん性にあればカテゴリー2、集簇性にあればカテゴリー3、微細分枝状の石灰化が区域性にあればカテゴリー5、のように判定します。
カテゴリー5と判定された場合は、がんである可能性が非常に高いと考えます。カテゴリー4(例えば多形性、集簇)の場合は、がんの可能性が30-50%と言われています。カテゴリー3の場合は、良性の可能性が高いですが、5-10%くらいがんの可能性もあります。カテゴリー3以上は「要精検」となります。
基本的な判断基準は上に書いた通りですが、時に紛らわしい場合があります。以下に例を挙げます。
・線維腺腫の石灰化…石灰化ができ始めの時は、多形性・集簇性に見える場合があります(やや丸みを帯びているのでわかることが多いですが時に迷う場合があります)。
・温存術後に見られる異栄養性石灰化…時間がたつと大きな石灰化になっていくので良性とわかりますが、やはりでき始めの時には局所再発ではないかと心配する場合があります。
・MLT(mucosele-like tumor)の石灰化…少し変わった形をしているため悪性に見える場合があります。
・悪性の場合でも、微小円形石灰化で数が少ない場合は、カテゴリー3以上に取れない場合があります。経過を追うことによって数が増え、要精検となる場合がたまにあります。以前、研修でお世話になった病院で、3年以上経過を追って、石灰化が少し増えたのでマンモトーム生検をしたら非浸潤がんだった症例もありました。微小円形の石灰化(分泌型)はがんでも見られますが、多形性や微細分枝状の石灰化(壊死型)と異なり、進行がゆっくりなことが多いので、強く悪性を疑わない場合には、カテゴリー3でもマンモトーム生検までしないで経過をみる場合もあります。
患者さんの中には、検診で「微細石灰化」という結果が届いただけで「がんなんだ…」と思い込んで受診される方もいらっしゃいます。実際はカテゴリー3での「要精検」のケースが多いですので微細石灰化=がんではありません。微細石灰化で「要精検」となった場合は、通常、まず超音波検査で病変が見えるか確認します。見えれば細胞診、または組織診を行ないます。MRも診断の補助になりますので、超音波検査で見えない場合には特に判断のためには有用です。これらの検査結果を踏まえた上で、経過観察にするか、ステレオガイドのマンモトーム生検まで行なうかを判断します。超音波検査やMRで病変が確認できないような乳がんは一般的に進行が遅いおとなしいタイプですので経過観察も選択肢に入ります。慌てずに順序を追って検査を受けるようにして下さい。
*ご質問をされる前にhttp://hidechin-breastlifecare.blogspot.jp/2013/10/blog-post.htmlをご覧下さい。